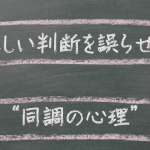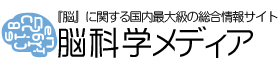ヒトをヒトたらしめる要素として、様々な能力や性質を挙げることができる。たとえば、『道具の使用』や『社会の構築』、または『言語の使用』などである。とはいえ、これらの要素は必ずしもヒトのみに限られるものではない。たとえば、ヒトと同じ霊長類に属するチンパンジーやボノボ(=ヒト科チンパンジー属)であれば、道具の使用や社会の構築を可能としており、イルカやヨウム(=洋鵡:インコ科ヨウム属)であれば、自らが生み出す音を用いて仲間への情報の伝達を図るという点で、簡易な言語の使用を可能としている。
道具の使用や社会の構築、または言語の使用を可能とするためには、一定の知能が必要となる。それゆえ、道具や言語を使用し、または社会を構築している動物には『一定の知能がある』と結論付けることができる。この点、一般的にはヒトと他の動物を区別するために『知能の有無』が基準として用いられる場合があるが、ヒト以外の動物が道具や言語を使用し、または社会を構築していることを考えると、ヒトと動物を区別する基準を『知能の有無』とするのは適切ではないといえる。そこで、ヒトと動物を区別する基準として『知能の有無』ではなく、『知能の高さ』を用いることが適切といえる。
ヒトの知能の高さがどの程度であるかを把握する際に、人が行い、なおかつチンパンジーやボノボ、イルカやヨウムなどの一部の動物が行う『道具の使用』『社会の構築』『言語の使用』の度合いが一つの基準となる。なお、『道具の使用』と『社会の構築』は、『言語の使用』によってより高度なものへと進化・発展させることが可能となる。この点で、『言語の使用』は他の二つの能力よりも高次に属する能力であるといえる。
以下では、言語の特殊性に焦点を当て、言語能力がヒトの進化や社会の構築にどのような影響を与えたのかについてみていく。
【主な目次】
1.言語の特殊性
・1-1.言語による“道具の進化”
・1-2.言語による“社会の発展”
2.言語獲得までの過程と、言語獲得によって得られた能力
・2-1.身体的特徴の変化による“発声の実現”
・・2-1-1.二足歩行と筋力の変化
・・2-1-2.高度な発声の獲得
・2-2.脳の肥大化による“心の誕生”
・・2-2-1.協調性と推論
・・2-2-2.長期記憶と抽象的思考の発達
・・2-2-3.短期記憶と論理的思考の発達
1.言語の特殊性
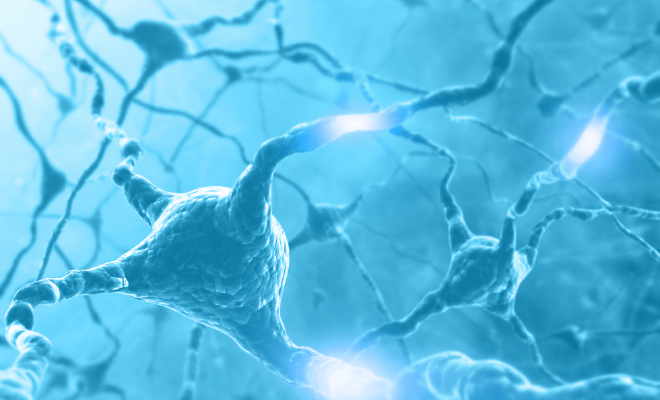
言語は、活用次第で道具や社会を進化・発展させる要素となる。ヒトのこれまでの歴史を振り返ると、言語が道具や社会を大きく進化・発展させてきたことが分かる。以下では、ヒトのこれまでの歴史の中で言語がどのようにして道具や社会を進化させてきたのかについて概観する。
・1-1.言語による“道具の進化”
“より高度な言語”を駆使することで“より高度な道具”を実現した例としては、今から20万年~3万年ほど前に存在していたネアンデルタール人とホモ・サピエンスの事例を挙げることができる。
ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、言語の運用能力に大きな開きがあったことが分かっている。ホモ・サピエンスは利便性の高い石器を考案すると、高い言語能力を用いて子孫へと継承させていった。こうした『言語による技術の継承』が行われることによって、世代を重ねるごとに利便性の高い石器が生み出されるようになった。これに対してネアンデルタール人は、高い言語能力を有していなかったため、石器に関する技術を子孫に継承させることができなかった。それゆえ、世代を重ねても石器の利便性が向上することはなかった。
こうした要因が一因となり、ネアンデルタール人は今から3万年ほど前に絶滅した。
・1-2.言語による“社会の発展”
“より高度な言語”を駆使することで“より高度な社会”を構築した例を考える上で、『ヒトの社会』と『ハチやアリの社会』の比較が参考になる。
“社会”とは、『様々な役割を持った個々によって構成される集合体』を指す。“社会”を地球上で初めて構成した生物は、ヒトではなく昆虫(ハチやアリ)である。
今から1億年ほど前に海中から陸上へ進出した生物は昆虫へと進化を遂げ、ハチやアリの共通の祖先は集団で生活を行うようになった。その集団の中で、個々の構成員(ハチやアリ)は育児や教育、巣作り、食糧の調達、戦闘などの役割を担うようになった。ハチやアリが持つこのような性質は、生物学では“真社会性”と呼ばれている。なお、二足歩行を可能とする類人猿が登場するのは、昆虫が社会を形成してから数千万年後(今から700万年前)である。
現在、ハチやアリなどの昆虫が登場してから1億年が経過し、そして人類が登場してから700万年が経過している。かつてハチやアリが作り出した社会は、現在でも数百万年前の形から変化していない。これに対して、ヒトによって形成された社会は今日に至るまでに大きな変化を遂げている。
ヒトの社会では、今から1万2000年前に農耕と牧畜が開始された。農耕と牧畜の技術は言語によって継承され、世代を追うごとに進化を遂げた。また、今から5000年~4000年前には文字が登場し、法律や規則などによって社会制度が構築されていった。
言語は、社会制度のみならず社会における様々な技術も進化させた。例えば、かつては徒歩や馬、または船に限られていた交通手段は、現在では自動車や高速鉄道、航空機へと進化し、数百km、数千km離れた場所に数時間で移動することを可能とした。通信手段の分野では、携帯電話やスマートフォンを用いて情報の伝達や取得を行うことが可能となった。医療分野では、かつては不治の病とされていた病気の克服が可能となった。より身近な生活分野では、たとえばエアコンの登場によって夏は涼しく冬は暖かく過ごすことが可能となり、流通網や冷蔵・冷凍技術の発達によっていつでも新鮮な食糧を得ることが可能となった。
こうした社会における様々な技術の発展は、技術の継承と蓄積を可能とする言語によって実現された。これは言い換えれば、言語や文字を駆使する能力を持たない他の生物では、意図的に社会を発展させることができないことを意味している。このことは、言語や文字を駆使する能力を持たなかったハチやアリが今日に至るまでに意図的に社会を発展させることができていないことからも分かる。
2.言語獲得までの過程と、言語獲得によって得られた能力
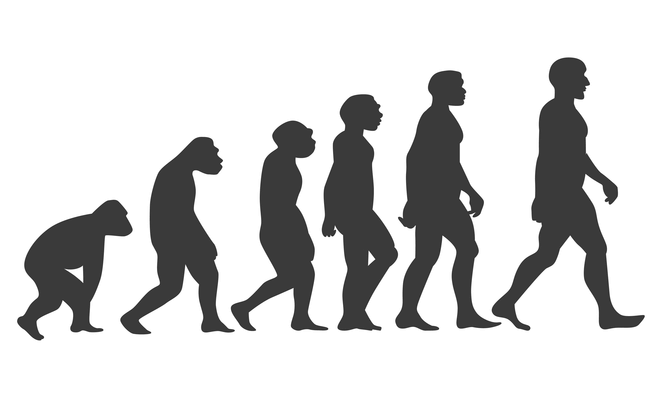
言語は、技術や社会を発展させる要素となる。なお、技術や社会を発展させるためには一定の知能が不可欠となることから、言語の運用能力と知能には一定の関連性があるといえる。
先述したように、ヒトと動物を区別する基準は『知能の有無』ではなく『知能の高さ』とすることが適切である。そして、言語能力と知能に一定の関連性があるのであれば、ヒトが言語を獲得するに至った過程と、それに連なる知能の変化についてみることで、言語能力と知能がどのように関連しているのかを知ることができる。よって以下では、ヒトが高度な言語能力や知能を獲得するに至った要因や、言語の獲得によってどのような能力を得ることができたのかについてみる。
・2-1.身体的特徴の変化による“発声の実現”
言語を用いる方法は、2つに分類することができる。一つは『文字による表記』であり、もう一つは『音声による表現』である。この2つの方法は同時期に獲得されたものではなく、『音声による表現』が発生(=今から数十万年~数百万年前に発生)した後に、文字が生み出されたことによって『文字による表記』が発生(=今から約5000年前に発生)した。
・・2-1-1.二足歩行と筋力の変化
ヒトの祖先となる霊長類は、今から約700万年前に二足歩行をはじめた。この二足歩行の実現が後に、ヒト特有の“発声”を可能とさせる要因となった。
今から約230万年になると、食物を噛み砕く際に用いられる咬筋や側頭筋に退縮がみられた。従来の類人猿では大きな咬筋が頭頂から側頭を覆っており、食物を咀嚼するたびに下向きの強い圧力が頭部にかかっていた。そのため、脳を肥大化させる要因があったとしても、咬筋や側頭筋に阻まれることで脳が肥大化することはなかった。この点、咬筋や側頭筋が退縮したことによって、脳の肥大化は妨げられないようになった。
今から約50万年前になると、ヒトは意図的に火を使用することを覚えた。肉を調理して摂取することにより、従来よりも噛む力が必要とされなくなった。それゆえ、顎の筋力の必要性が低下し、顎が退化していった。また、火で調理した肉は体内で消化されやすいため、従来よりも腸の機能が必要とされなくなった。これにより、それまで腸の活動に用いられていたエネルギーは脳の成長に用いられるようになった。
咬筋と側頭筋の退化に加え、顎が退化したために頭蓋骨を覆っていた咀嚼筋が減少し、腸の活動に用いられていたエネルギーが脳の成長に用いられるようになったことから、ヒトの脳はさらに肥大化し、高度な言語を運用できる条件が整っていった。
・・2-1-2.高度な発声の獲得
発声を行う場合、声帯を振動させるために肺から息を送り、息を口蓋に衝突させ、状態を変化させた舌や歯や唇を活用して様々な音に区切る『調音』とよばれる作業が必要となる。この調音により、異なる音が集合したことで意味を持つ“単語”が生み出される。
発声には呼吸の意図的な制御が必要であるが、呼吸は本来、自律神経系によって制御される無意識の活動であった。この点、脳が肥大化することによって大脳の運動皮質と延髄の呼吸を制御する神経核が連携するようになったことで、呼吸の意図的な制御が可能となり、発声が可能となった。
脳の肥大化が進むにつれてそれまで以上に多様性に富む音声の発生が可能となり、それゆえ言語(音声)によって伝達できる情報は複雑化していった。
ヒトは直立二足歩行を獲得したことにより、首が長くなり、喉頭(こうとう)が下がって咽頭(いんとう)が長くなった(=咽頭内の空間が広くなった)。これにより、ヒトは調音の能力を身に付けた。なお、ヒトが調音を可能としているのに対して、ヒトと同じ霊長類に属するチンパンジーは脳の大きさや発声器官の構造上、調音が不可能となっている。
以上のように、直立二足歩行による喉の構造の変化や、火の使用による腸や顎の構造の変化に起因する脳の肥大化が要因となり、地球上に存在するあらゆる生物種の中でヒトのみが複雑な『音声による表現』を可能とし、言語による高度な情報の伝達手段を獲得した。
・2-2.脳の肥大化による“心の誕生”
ヒトは直立二足歩行や火の使用によって音声を生み出すことを可能とし、音声による複雑な情報伝達を可能とした。この点、言語を単なる“情報の伝達のツール”と定義付けるのであれば、前述したイルカやヨウムを“言語を駆使する生物”とすることも適切といえる。もっとも、言語を“情報の伝達のツール”であると同時に、“思考のツール”と定義付けるのであれば、イルカやヨウムを“言語を駆使する生物”とすることは不適切といえる。
言語は、狭義の意味においては“情報の伝達のツール”に留まるが、広義の意味においては“思考のツール”をも含んだ要素である。この点、言語を“情報の伝達および思考に用いるツール”と定義付けるのであれば、イルカやヨウムが言語を駆使して思考することができず、ヒトのみが言語を駆使して思考を可能としていることから、広義の意味での“言語の使用”は、ヒトのみに可能な活動であるといえる。
直立二足歩行の獲得に起因する脳の肥大化は言語の使用を可能とし、ヒトは言語を駆使することで脳の肥大化を加速させた。こうして加速した脳の肥大化は、ヒトと他の動物の違いを決定付ける“言語以外の性質”の獲得を実現するようになった。例えば、協調性や推論、長期記憶と抽象的思考、短期記憶と論理的思考などである。
・・2-2-1.協調性と推論
様々な要因から脳を肥大化させていったヒトは、他の動物や自然との生存競争の中で生き残るべく、集団内での協調性(チームワーク)を身に付けるようになった。身に付けられた協調性は後に、狩り以外の様々な場面でも発揮されるようになった。
かつてヒトは生活をより安定したものにするために、野営地を作ることで生活の拠点を設けた。野営地を中心とした集団生活では分業が求められ、ある者は野営地を離れて狩りを行い、ある者は野営地や子どもを護衛する役割を担った。狩りによって獲得された食糧は、野営地の構成員に等しく分配されなければ集団を維持することができなかったため、狩りに参加していない野営地の構成員にも等しく分配された。このような“集団を維持するための圧力”は、結果的に集団内で“相手の意図を推測する”という能力を高めていくことになった。このような“相手の意図を推測する”能力は、集団内での生活や狩りの場面だけでなく、敵対する集団との戦闘においても重要な役割を果たした。敵対する集団との戦闘で相手に勝利するためには、敵の意図を推測し、先手を打つことが求められた。また、戦闘中に仲間の意図を推測して協力することで勝率を高めることができた。敵対する集団同士の戦闘においては、協力する集団は協力しない集団よりも優位に立つことができたため、仲間の意図を推測する能力や協調性を持たない集団は淘汰され、そうした能力を持つ集団だけが生存し続けることになった。
ヒトと最も近い種族とされるチンパンジーでさえ、“協調性”や“相手の意図を推測する能力”を有していないことが実験によって確認されている。
ある実験において、ヒトの子どもに容器の蓋の開け方を教えた後、容器の蓋の開け方を知っている子どもから見える場所で、大人がその蓋を開けようとしても開け方が分からないふりをした。それを見た子どもは、その時に自分がしていた作業を中断し、困っている大人を助けるために大人のところへ向かった。同様の実験をチンパンジーに対して行なったところ、チンパンジーは同じ状況に置かれても協力する素振りを見せなかった。
この実験の結果から、ヒトの社会が発展した要因の一つは、他の構成員の意図を推測し、協調行動をとれる“社会性”にあることが分かる。
相手の意図を推測し、意志の疎通を図り、協調することによって、ヒトは集団として、単独で活動するよりもはるかに多様かつ効率的な活動を行うことができるようになった。こうした“協調性”や“相手の意図を推測する能力”が求められた生活環境の中で、ヒトは“推論”の能力を身に付けるようになる。この推論の能力によって、相手の意図を正確に把握し、高い精度で協調性を発揮することが可能となった。なお、こうして獲得された推論の能力は、後にヒトの言語能力の向上に大きな影響を与えることになる。
・・2-2-2.長期記憶と抽象的思考の発達
推論の能力を獲得したヒトはその能力を駆使するうちに、次第に記憶を蓄積し、過去の記憶を遡る能力を高めていった。これにより、過去の記憶を遡って複数の情報を整理し、眼前の相手の状態や心理・思考をより正確に推測できるようになった。こうした推測を繰り返すことにより、脳内では扁桃体などの感情をコントロールする中枢部分や自律神経が発達していった。
過去の記憶を遡る能力を獲得したヒトは、記憶力を強化させていった。記憶力の強化は脳のさらなる発達をもたらし、膨大な情報の長期記憶が可能となった。長期記憶を獲得したヒトはその後、長期記憶の一部を取り出し、それらを組み合わせることで計画や筋書きを構成する能力(=構成力)を身に付けた。この能力により、その時点における推論だけなく、過去の情報を呼び起こし、未来における中長期的な利益を実現するための推論が可能となった。
“長期記憶”と“記憶を用いて情報を構成する能力”を獲得したヒトは、言語を用いて目の前にある事柄を思考するだけでなく、過去や未来に関する事柄や、眼前に存在していない“概念”などの抽象的な事柄を思考することが可能となった。こうした抽象的な思考は、後に宗教や芸術の分野を切り開いていくことになった。
なお、過去の記憶と未来の推論はヒトの言語体系(文法構造)にも変化をもたらし、ヒトは言語を用いて過去や未来を指す“時制”を扱うことができるようになった。
・・2-2-3.短期記憶と論理的思考の発達
ヒトの脳は進化の過程で“長期記憶”だけでなく、“短期記憶”も身に付けた。長期記憶が過去の経験(『学校を卒業した』、『友人と食事をした』という情報)や物事の意味(『りんご』、『自動車』、『勉強』の概念や定義に関する情報)の記憶であるのに対して、短期記憶は特定の作業を行う際にのみ保持される記憶である。たとえば、現在の時刻が『12時30分』であるといった情報の記憶や、天気予報で明日の気温が『22℃』であるといった情報の記憶、または『昨日の食事は何だったか?』といった質問内容(情報)の記憶である。長期記憶が長時間に渡って(場合によっては一生を通じて)保持される記憶であるのに対して、短期記憶は特定の作業(=時間や天気を知る、質問に答えるという作業)が終わると失われる記憶である。なお、脳の進化の過程で獲得された短期記憶は、後に“論理的思考”の実現を可能とした。
・・・2-2-3-1.短期記憶に基づく情報処理
ヒトの短期記憶の容量は、成長とともに増加することが確認されている。まだ歩行ができない乳幼児(1歳前後)の場合は、2つ程度の短期記憶(=情報のまとまり)しか保持することができない。そのため、乳幼児は思考の際に2つの以上の情報を結び付けることができない。たとえば、『リンゴ(の数)よりもバナナ(の数)の方が多い・少ない』といった2つの情報の比較が、乳幼児の思考の限界となる。
就学前(4~5歳)になると、子どもは3つの短期記憶を保持し、それぞれの関係を処理できるようになる。たとえば、『4+5=9』といった記号を用いる足し算がこれにあたる。この計算には、『4』、『+』、『5』という3つの情報を同時に記憶し、処理することが求められる。そのため、3つの短期記憶を保持できるようになって初めて、足し算や引き算などの計算を行うことができるようになる。
就学後(6歳~11歳)は4つの短期記憶を保持することができるようになり、それぞれの関係を処理できるようになる。たとえば、『12:36は15:45と等しいか否か』といった比率の計算がこれにあたる。この比率の計算には、『12』、『36』、『15』、『45』という4つの情報を同時に記憶し、処理することが求められる。そのため、4つの情報を記憶できる場合にのみ計算が可能となる。
ヒトの短期記憶の容量は、2歳頃から11歳頃にかけて増加していく傾向がみられる。なお、ヒトは成人であっても一度に4~5つ程度の短期記憶(=情報のまとまり)しか覚えられないことが実験によって確認されている。(ただし、特定の情報に関して事前にリハーサルを繰り返すことで、一時的に5~9個のまとまりの記憶が可能になることが確認されている。)
・・・2-2-3-2.短期記憶と論理的思考の関係
短期記憶は、ヒトの論理的思考に不可欠な要素となる。論理的思考とは、『因果関係に基づき、結論に至る展開を想像する知的活動』を指す。論理的思考では、結論に至るまでに複数の情報を記憶し、処理する必要がある。それゆえ、複数の短期記憶を保持できる場合にのみ、論理的思考が可能となる。
論理的思考の例の一つとして、以下の展開が挙げられる。
【前提から導かれる結論】
◆前提1.……生物は、いつか必ず死ぬ
◆前提2.……ヒトは、生物である。
◆結論 ⇒ ヒトは、いつか必ず死ぬ
上記の2つの前提から論理的に結論を導くためには、2つの前提を記憶し、処理する必要がある。このことから、論理的思考には短期記憶が不可欠であることがわかる。
幼い子どもが論理的な思考を苦手とするのは、短期記憶の限界が論理的思考に制限をかけているためである。これは言い換えれば、成長によって複数の情報を同時に記憶し、処理することを可能とすることで、論理的に矛盾のない思考が可能となることを意味している。
なお、複数の情報を同時に記憶することができない他の動物(生物)は、論理的思考を行うことができない。その例として、アナバチの行動パターンが挙げられる。アナバチは獲物を捕って巣に戻る際に、獲物を巣穴の外に置き、巣の内部を点検してから獲物を中に引き入れて幼虫に与える習性を持つ。アナバチが巣の内部を点検している間に誰か(=人)がその獲物を数cmだけ移動させると、巣から出てきたアナバチは再びそれを巣穴の近くに置き、巣の内部を点検する作業を繰り返す。
アナバチがこうした行動をとるのは、『巣穴の内部が安全だった』という記憶と『獲物を巣穴の外に置いた』という2つの記憶を同時に保持することができず、“獲物を巣穴の外に置いた後に巣の内部を点検し、安全だった場合に獲物を中に引き入れる”という一つの流れで行動することしかできないためである。
この点、短期記憶に基づく論理的思考が可能なヒトであれば、『外部に置いた』という情報と『内部が安全』という情報の2つを同時に記憶し、処理することができるため、内部を一度確認した後は外部に置いた物が移動していた場合でも、2つの記憶を統合して判断し、同じ行動を繰り返すことはない。
短期記憶に基づく論理的思考がヒト特有の能力であるという点は、『交互』の概念の理解が可能であるか否かを調べる実験からも明確になっている。
エサの隠し場所を『右、左、右、左』と交互(=単純交代)に設定した場合、この法則はヒト以外の動物でも理解できることが確認されている。これに対して、エサの隠し場所を『右、右、左、左、右、右、左、左』のように同じ場所を2回1組として交互(=二重交代)に設定した場合、この法則を理解できるのはヒトだけであることが確認されている。
これは、ヒト以外の動物は短期記憶の能力の関係から、一つ前の情報と二つ前の情報の両方を記憶することができないために『一つ前が右、二つ前も右だから、今回は左である』という、短期記憶に基づく論理的思考ができないことが原因となっている。
こうした短期記憶の能力は、ヒトが用いる言語(文章)における“入れ子構造”(=回帰的階層構造)の作成に不可欠となっている。入れ子構造(=回帰的階層構造)とは、言語(文章)の中に他の独立した言語(文章)が組み込まれた文章を指す。
【入れ子構造を持つ文章と持たない文章】
◆入れ子構造(回帰的階層構造)を持たない文章
例:『彼は肉を食べる。』
◆入れ子構造(回帰的階層構造)を持つ文章
例:『私は、彼が肉を食べるということを知っている。』
⇒“私は知っている”という文章の中に、“彼が肉を食べる”という独立した文章が組み込まれている。
ヒトは今から約20万年前に、短期記憶の発達から上記のような入れ子構造(=回帰的階層構造)を持つ文章を構成する能力を獲得した。こうした“回帰性”は、音声(言語)を用いてコミュニケーションを行う他の動物にはみられない、ヒト特有の能力となっている。
上記の例のような“自分以外の他者が~であること知っている”といった複雑な入れ子構造(=回帰的階層構造)の文章を生み出すことができるようになったのは、複数の情報(他者に関する情報と、自分が知っているという情報)を同時に保持できる短期記憶の能力が発達したことに加え、他者の意図や考えを推測する能力である『認知機能』が発達したことが要因となっている。
こうして、短期記憶による論理的思考の発達や長期記憶による抽象的思考の発達により、ヒトの言語能力と思考力はさらに向上していくことになった。