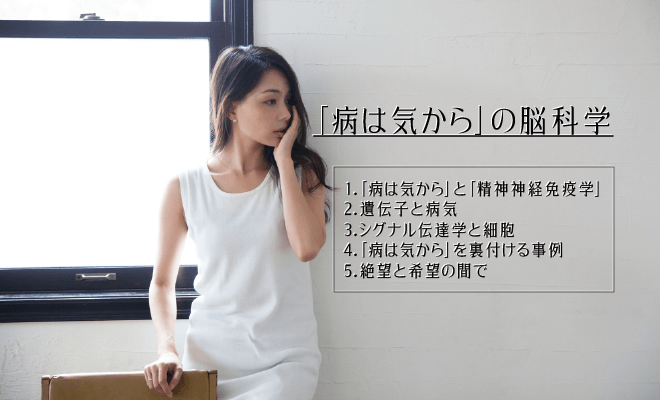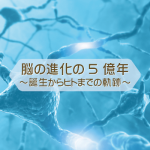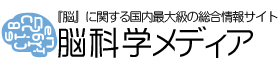「病は気から」という言葉は、多くの人が一度は耳にしたことがある言葉である。とはいえ、その真偽については半信半疑という人も多いかもしれない。「ストレスは身体によくない」という漠然としたイメージは湧いても、ストレスや心理状態、気持ちが具体的にどのように身体に悪影響を与えるのかは詳細に知られているわけではない。そこで以下では、「病は気から」という説について脳科学とその他の学術分野からみていく。
【目次】
1.「病は気から」と「精神神経免疫学」
2.遺伝子と病気
3.シグナル伝達学と細胞
4.「病は気から」を裏付ける事例
4-1.ラットの事例
4-2.ジョーと父親の事例
4-3.マリアと母親の事例
5.絶望と希望の間で
1.「病は気から」と「精神神経免疫学」
「病は気から」という説と密接に関連するのが、「精神神経免疫学」という学術分野である。
生体(生物の身体)は、環境の変化に適切に対応するべく“生体防御系”という機能を有している。例えば、外部環境の変化によって内部環境(体内)に悪影響が及ばないよう、内部環境を一定に保つ“恒常性(ホメオスタシス)”という機能がある。その中心となるのが、神経系、内分泌系、免疫系である。神経系は身体の内外の情報を伝達する役割を果たし、内分泌系は神経系から情報を受け取って各種の臓器に対してホルモンを分泌する。免疫系は、外部からの悪しき侵入者を駆逐するために機能する。
神経系、内分泌系、免疫系はそれぞれ独立して機能しているのではなく、相互に密接かつ合理的に調節しあっていることが研究によって明らかにされている。これらのネットワークを介して、ヒトの心と身体は結びついている。
ヒトがストレスを受けたとき、脳から抹消(各器官・部位)へ向けて、主に二系統の変化、すなわち神経系の反応と内分泌系の反応が免疫系に影響を与えることが分かっている。この際に特に重要な役割を果たすのが、副腎(ふくじん)である。副腎の髄質部分は神経系の刺激を受けてアドレナリンやノルアドレナリンを分泌し、皮質部分は内分泌系の刺激を受けてグルココルチコイドを分泌する。
これらの分泌は、身体的なストレスによってのみならず、精神的なストレスによっても生じる。ストレスが過度で慢性的であれば、分泌が長期間かつ過剰に起こる。分泌される物質の多くは、免疫細胞の活性に抑制的な作用を持つことが知られている。すなわち、過度なストレスによって免疫が低下し、身体の各器官や部位に悪影響を与えることになる。
近年では、精神神経免疫学の領域だけでなく心身医学の領域全般でもストレスの影響について研究されている。また、“サイコオンコロジー”の分野では、がんを対象とした精神免疫学の研究が盛んである。サイコオンコロジーとは、心理学(psychology)と腫瘍学(oncology)を合わせた造語である。主な目的は、がんが心に与える影響と、心や行動ががんに与える影響を調べ、Quality-of-life(生活の質)の向上や、がん罹患の減少、生存期間の延長を図ることにある。
このように、近年では心理的な要因が身体に一定の影響を与えることが医学の分野での常識となっている。「病は気から」という考えは、今や科学的に裏付けられている作用である。
2.遺伝子と病気
病気を引き起こす要因は、ふたつに大別することができる。ひとつは先天的要因(内的要因)で、もうひとつは後天的要因(外的要因)である。先天的要因(内的要因)は生まれながらに有する要因(例:遺伝子の異常など)であり、後天的要因(外的要因)は生活する中で影響を受ける要因(例:細菌やウイルス、身体的・精神的ストレスなど)である。
意外と知られていない事実として、遺伝子の異常などの先天的要因は、ヒトが患う病気の原因の2%程度という研究報告がある。すなわち、ヒトが患う病気の原因の98%程度は後天的な要因である。精神的なストレスは、そのひとつである。
がんなどの大病は遺伝による影響が大きいと考えられがちだが、それでも遺伝子が直接的な原因になっているのはわずか5%程度であり、日常における食生活や運動量、睡眠時間、ストレスの量などが原因となることが多い。例えば、前立腺がんの患者たちが90日間にわたって食事と生活様式を変えただけで、腫瘍(がん細胞)の形成に不可欠な生物学的過程を阻害する遺伝子が活性になった(すなわち、がんの発生を抑えた)という研究結果がある。
生命は、一般的に考えられているほど遺伝子に支配されているわけではない。遺伝子にはさまざまな情報が組み込まれており、そのいずれかが発現することで細胞を生み出しヒトの身体をつくりあげる。しかし、遺伝子はどの情報を発現させるかを自ら決められるわけではない。すなわち、遺伝子は“自己創発”ができない。環境の中の何かが引き金にならなければ、遺伝子は発現(活性化)しない。
遺伝子は細胞を生み出すが、細胞の状態は細胞をとりまく環境によって制御されており、遺伝子はほんのわずかしか関わっていない。つまり、環境こそが細胞の在り方を決定する。この環境のひとつが、ストレスである。この分野については、「シグナル伝達学」という最新の学術分野で研究が進んでいる。
3.シグナル伝達学と細胞
シグナル伝達学では、細胞が環境からのシグナル(情報)にどのように反応するかについて研究されている。環境からのシグナルが細胞内の化学反応を引き起こし、遺伝子の発現パターンを変化させる。それにより、細胞がどのように分化されるかが制御され、細胞が生き残れるかどうかが決定する。生物の活動や生存する上での方向性は、環境に直接的に関係する。
ヒトの身体では、毎日のように何十億という細胞が寿命を迎えて亡くなっていく。これは細胞にあらかじめプログラムされているものであり、アポトーシスと呼ばれる現象である。例えば、腸の細胞は72時間ですべてが新しいものに入れ替わる。(若い女性とっては、“肌のターンオーバー”といったほうが伝わりやすいかもしれない。)
細胞は、常に『成長・増殖』か『防衛』のいずれかの反応をとる。そして、その両方を同時とることができないという特徴を持つ。細胞の成長・増殖には、エネルギー源となる栄養素のやりとりが不可欠である。細胞が成長・増殖の状態にあるときは生体システムが環境に対して開かれた状態となる。つまり、細胞は自由に食物を取り入れ、排出物を出す状態となる。
これに対して、身体がストレスを感じると細胞は防衛状態となる。防衛状態になると、細胞は感知された脅威に対して防御壁をつくる。防御壁がつくられている間は、細胞は外部から栄養素を受け取ることができなくなる。細胞は存続のために常に栄養素が必要であるため、外部から栄養素を受けるとことができない期間が長く続くと、その存在を維持できなくなる。ストレスを感じると身体に悪影響を及ぼすのは、ストレスを感じている間は細胞が防衛状態に入り、成長・増殖できないためである。すなわち、栄養を摂取してエネルギーを生み出すことができず、細胞は新生されない。
これが、ストレスによって身体に悪影響が及ぶメカニズムである。すなわち、「病は気から」たるゆえんである。
4.「病は気から」を裏付ける事例
身体がストレス反応を起こすと、細胞がもつ自己保全や自己修復のための機能は急停止する。ストレスはときに、がんなどの大病を引き起こす。また、ストレスはがんを発症させるだけでなく、その進行度合いにも影響を与える。過度なストレスはがんの進行を早め、軽微なストレスはがんを抑制することもある。
以下では、ストレスががんに与える影響を明確にした事例を紹介する。
4-1.ラットの事例
絶望感(ストレス)と病気をつなぐメカニズムを明確にするために、ある実験が行われた。この実験では、ラットを3つのグループに分けた。第1グループには、電気ショックが与えられたが逃げ道も用意された。つまり、逃げ方を学習すればいつでも逃げられるようにした。第2グループには、電気ショックが与えられたが逃げ道は用意されなかった。第3グループには、電気ショックが与えられなかった。
なお、電気ショックを与える前に、すべてのグループのラットの腹部にがん細胞を植え付けた。植えつけるがん細胞の数は綿密に管理され、通常の状態であれば半数のラットが生き残り、半数のラットが命を落とすように設定された。3つのグループのマウスは、いずれも食事や生育環境、がん細胞による負担といった外的要因はすべて同じものとされ、各グループの違いは“心理的体験”のみだった。
実験開始後、逃げ道が用意された第1グループのラットはすぐに逃げる方法を学習し、電気ショックを逃れた。これに対して逃げ道が用意されなかった第2グループのラットは、無力感(諦め)を学習した。電気ショックを与えられなかった第3のグループのラットは、逃げることもトラウマを受けることもなかった。
実験開始から1ヶ月が経過すると、ショックを与えられなかった第3のグループのラットは、当初の計算どおり約50%だけが生き残り、残りの約50%が命を落とした。これに対して、逃げ道が用意されなかった第2のグループのラットの生存率は27%だった。このグループのラットを調べたところ、免疫系が弱まっていることが判明した。体内に侵入した異物を認識する“T細胞”は増殖せず、侵入したがん細胞との闘いを放棄していた。また、がん細胞やウイルスを撃退する“ナチュラルキラー細胞”も、その能力を失っていた。これは、解消できない絶望(ストレス)が要因となっている。
それでは、逃げ道が用意された第1グループのラットの生存率はどれくらいだったのだろうか。このグループの生存率は、63%だった。すなわち、電気ショックを与えられなかった第3のグループのラットよりも高い生存率だった。これは、自分で状況を制御できるという感覚や、被害を避けられるという感覚、さらにはショックを受けたときにその事態を回避できるという“希望”が、ストレスを緩和させ、免疫系を高めたことによるものだと考えられる。
4-2.ジョーと父親の事例
ジョーという末期がん患者の少年がいた。ジョーには、幼い頃に別れたままの、顔も知らない父親がいた。強力な化学療法を受けていたある日、彼は父親に手紙を書いて自身の病状を伝え、『一度だけでもフロリダから会いにきてほしい』と懇願した。母親は父親の居場所を知っていたので、その手紙を送ると約束した。やがて父親から『見舞いに行く』との返事が来て、ジョーは大喜びした。
父親の訪問を待つ間、化学療法の効果は思わしいものではなかった。ジョーの身体は次第に衰弱していった。しかし、彼は楽観主義者だった。自分の病気は治ると信じ、それまではあれこれ想像するだけだった父親に実際に会って、いろいろ知りたいと楽しみにしていた。
そのうちにジョーは多臓器不全を起こし、残念ながら終末が近いのは間違いないと思われた。母親は父親に一刻も早く来るようにと電話し、その晩にジョーに『父親が航空券を買ったので一週間すればやって来る』と伝えた。すると翌日、驚いたことにジョーの容体は持ち直した。ベッドから起きて病棟内を歩き、『父親がやって来る』と看護師全員に教えて回った。
待ちに待った訪問は、土曜日の予定だった。それまでの一週間、ずっとジョーは父親のために絵を描いたり、話をつくったり、歌を練習したりしていた。父親の見舞いを励みにして見違えるほど元気になったジョーを見て、医者はとても驚いた。
そして土曜日を迎えた。飛行機は午後2時に到着する予定だった。飛行場はさほど遠くないので、父親は3時半までには病院に到着すると思われた。しかし、3時半を過ぎても父親は姿を見せなかった。ジョーは待った。さらに待った。
結局のところ、父親は現れなかった。母親が電話をしても出ず、ジョーは留守電にメッセージを残したが父親は電話をかけてこなかった。ジョーは繰り返し『飛行機が遅れている』『タクシーが渋滞に巻き込まれた』と言っていたが、飛行機は予定どおりに到着していた。それでもジョーは、父親が来ると強く信じていた。彼の信念は全く揺らがなかった。
父親の到着予定時間から8時間が過ぎた頃、ようやく母親がジョーを説得した。ジョーは泣きだし、父親にすっぽかされたと言った。ジョーはその数時間後、容体が急変して亡くなった。
4-3.マリアと母親の事例
マリアという少女は8歳のときに白血病と診断され、強力な化学療法と、骨髄移植を医者から勧められた。しかし、マリアに適合する骨髄提供者が見つからなかった。そこでマリアの母親は、白血球型が一致することを期待して、もうひとりの子どもを産むという選択肢を採った。
母親が妊娠している間、医者はマリアの白血病が急激に悪化しないよう低用量の化学療法を施した。目的は、治癒ではなく時間稼ぎだった。新しい子どもが生まれたらすぐに臍帯血を採取し、可能であれば移植に使おうと考えていた。
弟妹をほしがっていたマリアは、母親が妊娠したと知って大喜びした。マリアの身体は化学療法のせいで衰弱していたが、心は元気さを失わず、『きっと治療の効果が出て病気が良くなり、立派なお姉ちゃんになれる』と看護師たちに話していた。看護師たちは『そのとおりね』と頷いたものの、マリアの血液検査の数値は、がん細胞がまだ消えていないことを示していた。
数ヶ月後、マリアの妹が生まれた。妹から採取された臍帯血はすぐに調べられたが、マリアの白血球型とは一致しなかった。母親はひどく落胆したが、マリアは『自分のがんはもう良くなったから、骨髄を移植してもらう必要はないの』と言った。しかし医者たちは、そんなことはありえないと考えていた。マリアに実施した低用量の化学療法では、白血病を治癒させるのは不可能だったからだ。
ところが、マリアは正しかった。検査の結果、がん細胞は跡形もなく消えていた。
5.絶望と希望の間で
マウスを用いた実験や、ジョーと父親、マリアと母親の事例から分かるように、絶望と希望が身体に与える影響は極めて大きい。絶望はときに命を奪い、希望はときに命をつなぐ。そして、希望が身体にもたらす好影響は、“何もない状態”よりも強い。
「病は気から」は、多くの研究や実験の結果から、科学的な根拠に裏付けられる。そして、絶望の中に希望を見出すことが、何の苦難もない状態よりも良い状態を実現することも分かっている。それゆえヒトは、むやみに絶望を回避するのではなく、絶望の中に希望を見出し、日々の困難に抗っていくことこそが大切であるということを心に留めておくべきである。真の健康と幸せを得るためには、困難と向き合い、闘っていくことこそが大切なのだ。
関連書籍
![]()