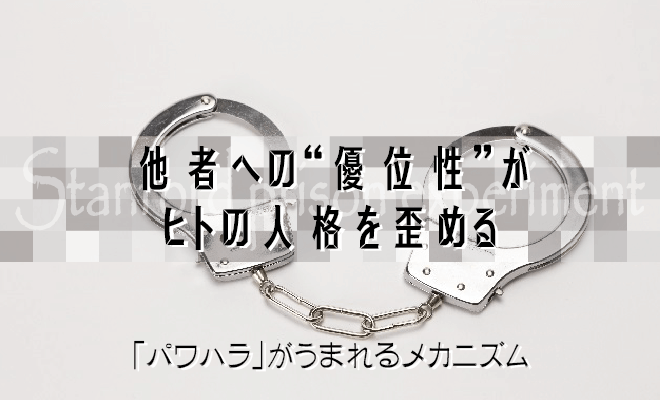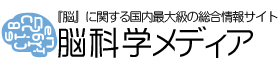2018年、数えきれないほどの「パワハラ(パワーハラスメント)」がテレビや雑誌、新聞などを賑わした。なぜこれほどまでに多くのパワハラが存在するのか。
ヒトの対人的な性格や人格は、先天的な要因以上に後天的な要因によって形成される。いわゆる「人当たりの良い人」と「人当りの悪い人」は、生まれた時点というよりも身を置く環境によって生じうる。
過去の心理学実験から、ヒトの性格や人格を歪める要因の一つとして“他者に対する優位性”が関係していることがわかっている。ヒトは、他者に対して自身の優位性を認識した際、支配や加虐の本能が発現しやすくなり、相対的な劣位にいる者に対して暴力的な行動をとる傾向がある。アメリカ・スタンフォード大学の心理学者であるフィリップ・ジンバルドが行った「スタンフォード監獄実験(囚人・看守実験)」は、これを如実に示している。
スタンフォード監獄実験
フィリップ・ジンバルドは、新聞広告に『刑務所生活に関する心理学的研究に参加する男性の志願者を求む(日給15ドル)』という求人広告を載せ、実験の被験者を募った。この実験では被験者を囚人と看守との2つのグループに分割し、囚人役は1日24時間、看守役は1日8時間、自身の役割を演じることで、それぞれの心理的な変化を観察することが目的とされた。75人の応募者の中から、家族調査、意見調査、面接調査によって心身ともに最も安定し、なおかつ精神的成熟度も高く、反社会的行為に関係したことのない(犯罪歴がない)者を被験者に選んだ。こうして選ばれた被験者は研究の内容を知らされた上で契約書に署名し、実験に参加した。集められた被験者は無作為にそれぞれ囚人10人と看守11人に分けられた。
数日後の実験開始日当日、囚人役の被験者が警察によって逮捕(=形式的な演出)される場面から実験が始まった。手錠をかけられ、取り調べを受け、指紋が採取された後に目隠しをされて“監獄”に見立てたスタンフォード大学の地下室に連行された。彼らはその監獄内で足に鉄鎖を付けられ、番号が記され囚人服を着用し、名前ではなく番号で呼ばれた。実験では発案者である心理学者のジンバルドが“総督”を務め、学生が“部長”を務めた。看守役の被験者には、『囚人に対する身体的懲罰や暴力が厳禁であること』と、『刑務所が有効に機能するのに必要な適度の秩序を所内で維持すること』、そして『事務的な最小限の注意事項』が伝えられ、サングラス、警棒、笛、手錠、鍵が与えられた。
実験開始後、看守役の被験者は命令口調の言動が顕著となり、囚人役に対して侮辱行為が行われるようになった。そして、囚人役の被験者が反抗的態度をとった際には懲罰が加えられるようになった。さらに実験が進むと、反抗的態度を取った場合だけでなく、囚人が会話や質問をした場合、または笑った場合にも懲罰が加えられるようになった。このような懲罰により、囚人は次第に目立った行動を取らなくなっていったが、それでも看守による攻撃的な行動が続くようになった。看守は日に日に独裁的・専制的・抑圧的になり、自身の判断で独自のルールを作りだした。囚人の反抗の度合いによって与える食事の有無や洗面・トイレの許可を決定するようになり、囚人同士に互いを悪く言わせることもあった。なお、看守役は1日8時間の三交代制であったが、8時間が経過した後も超過の報酬を要求することなく自主的に“実験”に参加する傾向が見られた。このような状況が継続することにより、10人の囚人の内5人に情緒的な抑鬱や強度の不安、号泣、怒り、心因性の発疹などの病的兆候がみられるようになった。
この実験では囚人役と看守役の被験者の人格変容が実験者の予想以上に早く進行したため、実験前に予定していた期間である14日間を切り上げ、6日間で中止された。
実験結果が示すものとは
この実験結果を分析すると、総監役のジンバルドや部長役の学生が看守役の被験者に懲罰の指示を行っておらず、さらには看守の攻撃的な行動はジンバルドや学生の目の届かない範囲で顕著であったことから、こうした看守の行動は、総監や部長に対する“同調”や“服従”ではないことがわかる。
この実験が示しているのは、ヒトが他者よりも優位な立場にあることを認識した場合、ヒトの本能(闘争本能)が発露するという点である。ヒトは“自己防衛”および“種の保存”の本能から他者に対する支配および加虐的行動をとる傾向にある。そうした支配・加虐的行動は、それを可能とする“権力”や“権威”を手にしたときに他者に対して現れやすくなる。ヒトが権力や権威を持つことは、“他者に対する優越感を得る”ことにつながる。囚人・看守実験では『看守=優位、囚人=劣位』の関係にあることから、看守は囚人に対して“他者に対する優越感”を抱き、支配・加虐的態度をとることになった。
“他者に対する優越感”によって人格を歪めないために
“他者に対する優越感”は、権力や権威を有する場合にのみ生じるものではなく、“他社に対して優れている要素がある”と自身が認識することによっても生じる。たとえば、「他者よりも知能が高い」という認識や「容姿が優れている」という認識、または「身体能力が高い」「知識が多い」「資産が多い」「役職が高い」といった認識がある場合にも生じうる。こうした社会的地位・能力の高さ(もしくは高いという主観的な認識)は、ときにヒトの人格を歪めることになる。いわゆる“美人は性格が悪い”“お金持ちは性格が悪い”“上司は性格が悪い”といった俗説は、こうした『他者への優位性がもたらす行動・態度・姿勢』によって裏付けられることになる。
ヒトが自身の身を置く環境によって人格を歪めないためには、常に自身を戒める自律の姿勢が重要となる。すなわち、自身よりも相対的に劣位の立場にいる社会的弱者に対してほど、許容・献身・奉仕の姿勢を意識することが重要となる。